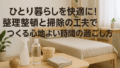洗濯物を畳むのが面倒…そう感じる一人暮らしの方は、実はたくさんいます。
忙しい毎日のなかで、「あとで畳もう」が積み重なって、結局部屋が散らかることもしばしば。
そんなあなたにおすすめしたいのが、“畳まない収納術”。
この記事では、洗濯物を畳まずにスッキリ片付く方法を25個紹介します。ハンガー収納・ボックス収納・動線の工夫まで、一人暮らしでも簡単に取り入れられるアイデアが満載。
手間を減らして、気持ちよく暮らすコツ、今日から始めてみませんか?
畳むのが苦手でも大丈夫!“畳まない収納”の考え方
なぜ洗濯物を畳むのが面倒に感じるのか?
洗濯物を畳むのが面倒だと感じるのは、あなただけではありません。一人暮らしの多くの方が、「時間がない」「やる気が出ない」「畳んだあとしまうのも面倒」と思っているのが現実です。仕事や学校から帰ってきて、干した洗濯物を見てため息…そんな日が続くと、ますます畳むのが億劫になりますよね。
実は“畳む”という行為は、想像以上に「工程数」が多く、時間も場所も使います。取り込む → 広げる → 畳む → しまう。これらを毎日・毎週繰り返すのは、意外と大きなストレスです。しかも誰にも見せるわけではない部屋着やパジャマ、タオル類までキッチリ畳む必要があるのか?と疑問に思うのは当然のこと。
「きちんと畳まなきゃ」という思い込みから解放されれば、生活が少しラクになります。洗濯物を畳むのが面倒なら、畳まなくていい工夫をすればいい。自分のライフスタイルに合った収納方法を見つければ、無理せず・ムダなく・心地よく暮らせます。
畳まなくても生活は回る
「畳まないとだらしない」そんなふうに思っていませんか?でも実際には、畳まなくても生活に支障が出ることはほとんどありません。特に一人暮らしなら、誰かに見られるわけでもなく、自分が困らなければそれでOK。清潔に保たれていれば、畳まなくても何も問題はありません。
たとえば、Tシャツをハンガーにかけたままクローゼットに入れたり、靴下や下着をカゴにポンと入れるだけで十分。実際、収納のプロやミニマリストの中にも「畳まない派」はたくさんいます。目的は「しまうこと」ではなく「使いやすくすること」なのです。
重要なのは、見た目より“動線”や“手間の少なさ”。畳まずに収納できる工夫を取り入れることで、洗濯のハードルがグッと下がります。自分にとって必要なものを、必要な形で収納すれば、それが一番心地よい暮らし方なのです。
「きちんとしなきゃ」思考を手放す
洗濯物を畳まないことに罪悪感を抱くのは、「ちゃんとしないといけない」という思い込みがあるから。でも、その“ちゃんと”って誰の基準でしょう?家庭によって、文化によって、考え方はさまざまです。今の生活スタイルに合わない「きちんと」は、手放しても問題ありません。
一人暮らしなら、自分が心地よいと感じる暮らし方を優先してOK。忙しい日々のなかで、あえて手間を省く工夫は、ズボラではなく「賢い選択」です。畳まない収納は、時間も手間も省けるだけでなく、「部屋を片付けるのが苦じゃなくなる」という心理的なメリットも大きいのです。
「毎回きれいに畳まないと…」というプレッシャーがなくなると、洗濯が少し楽しくなります。完璧じゃなくていい、自分なりの心地よさを大切にすることで、日々の暮らしに余裕が生まれるはずです。
時間・スペース・気力の節約になる
洗濯物を畳むことに使っている時間、どれくらいあるか考えたことはありますか?週に2〜3回、1回につき10〜20分使っていれば、1か月で約3時間以上が“畳む時間”に消えていることになります。しかも、その時間は座っているだけで他のこともできず、気分的にも重くなりがち。
畳まずに済ませることで、その時間をまるごとカットできます。さらに、畳んだ洗濯物をしまうための“引き出し”や“棚”を用意する必要もなくなり、収納スペースもシンプルに。余計な家具が不要になることで、部屋がスッキリします。
そしてなにより、「やらなきゃ…」という気力の消耗を防げるのが大きなメリット。畳まない収納は、家事に追われがちな一人暮らしの救世主になります。ちょっとした工夫で、時間も空間も、そして気力も守れる収納スタイルにシフトしてみましょう。
収納に求めるのは“見た目”より“使いやすさ”
SNSでよく見る整然と並んだタオルや洋服の収納、確かにきれいで憧れますよね。でも、それを毎回再現するのって、かなり大変。見た目ばかり気にして「続かない収納」になってしまっては意味がありません。
大切なのは、自分にとって“使いやすい”かどうか。畳まない収納は、毎日の生活で“使って戻す”のがとてもラク。ぐしゃっと丸めたシャツでも、パッと取り出せて、使ったら戻すだけ。シンプルでストレスがありません。
一人暮らしならなおさら、「見せる相手」はいません。だからこそ、自分がラクに使える収納法を選ぶのが正解です。見た目のきれいさよりも、“続けられること”が何より大切。畳まないという選択は、自分にやさしい暮らしの第一歩です。
ハンガー収納で解決!掛けるだけのクローゼット活用術
シャツ・ブラウスは全部ハンガーに
洗濯後のシャツやブラウスを毎回きれいに畳むのは、なかなかの手間。そこでおすすめなのが、「全部ハンガー収納」に切り替える方法です。干したハンガーごとそのままクローゼットに戻せば、畳む手間ゼロ。シワにもなりにくく、服の出し入れもラクになります。
ポイントは「同じ種類のハンガー」を使うこと。形がバラバラだと掛けたときにごちゃごちゃ見えてしまいますが、統一感のあるハンガーを選べば、自然と見た目もスッキリ整います。無印やニトリなどで揃えやすいシンプルデザインがおすすめです。
また、襟付きのシャツなどは畳むよりハンガーの方が型崩れもしにくく、アイロンがけの手間も減ります。「干す→そのまま収納」の一連の流れを作るだけで、洗濯が格段にラクになりますよ。
パーカーも“肩落ち防止ハンガー”でそのまま
「パーカーはハンガーにかけると肩が伸びて形が崩れるから…」と敬遠している方も多いのでは?でも最近では、“肩落ち防止ハンガー”や“厚みのあるふんわりハンガー”が手軽に手に入ります。これを使えば、パーカーも型崩れせずにきれいに収納できます。
洗濯後に干した状態のまま、ハンガーごとクローゼットにかけておけばOK。厚手の生地もふっくらしたままキープでき、クローゼットの中も整って見えます。畳むよりも断然ラクで、出すのも戻すのも一瞬。
収納のときは、フード部分が邪魔にならないよう、後ろに回してまとめておくとスッキリします。使わないときは薄く畳める折りたたみ式の肩幅ハンガーも便利。パーカーは“畳まない収納”の代表選手です。
ズボンは専用ハンガーで縦に省スペース収納
ズボンやパンツ類は、引き出しにしまうとシワになりがち。畳む手間もかかるので、こちらもハンガー収納がおすすめです。特に便利なのが“ズボン用マルチハンガー”。1本で4〜5本のズボンが掛けられるタイプなら、省スペースで収納できます。
干すときもこのハンガーに直接掛けておけば、取り込み後にそのままクローゼットへ。わざわざ畳む手間もなく、シワもつきにくいのが嬉しいポイントです。ポールに縦にぶら下げられるデザインなら、クローゼットのスペースを無駄なく使えます。
また、黒やグレーのズボンなど色が似ているものは、上下にずらして掛けることで一目で判別可能に。畳むよりも視認性が高く、朝の服選びもスムーズになります。ズボンは「吊るす」が一番ラクな収納法です。
洗濯後そのままクローゼットに入れる動線作り
畳まない収納を習慣化するには、“動線”がとても大切です。特に洗濯→干す→収納までの流れをスムーズにすることで、習慣化がしやすくなります。洗濯物を干す場所の近くにクローゼットがあるなら、干したハンガーをそのまま移動するだけで収納完了です。
もし間取りの関係で動線がバラバラになりがちな場合は、「ハンガーごと一時置き場」を設けるのもおすすめ。キャスター付きのハンガーラックを用意しておけば、移動がラクで、収納までの流れが効率的になります。
わざわざ「畳むためだけの時間」を取らなくても、日常の流れのなかで“ついで”にできる収納なら続けやすいですよね。習慣になるまでの最初のハードルを下げてくれる、動線の工夫は非常に効果的です。
ハンガー収納の落とし穴とその対策
便利なハンガー収納にも、いくつか注意点があります。一番の問題は「かけすぎてクローゼットがパンパンになること」。服がぎゅうぎゅうに詰まるとシワの原因にもなり、結局取り出しづらくなるという逆効果に。
この対策としては、まず“ハンガー1本につき1着”を意識すること。ついつい重ねてしまいがちですが、ゆとりを持った収納こそが、使いやすさの鍵です。また、季節外の服は一時的に収納ボックスに移すなど、スペースを確保することも大切。
さらに、ハンガー自体の数を制限するのもおすすめです。10本しかなければ、10着しか掛けられません。この仕組みが自然と“服を減らす”ことにもつながります。ハンガー収納は、うまく使えば一人暮らしの強い味方になりますよ。
ボックス・かごを使った“投げ込み収納”術
下着・靴下は仕切りボックスでざっくり収納
毎日のように使う下着や靴下を丁寧に畳んで引き出しにしまうのは、意外と手間ですよね。しかも、一人暮らしの忙しい生活の中では「時間があるときにやろう」と後回しになりがち。そこでおすすめなのが、「仕切り付きボックス」を使った投げ込み式の収納です。
100円ショップや無印良品などで手軽に手に入る布製や不織布のボックスに、小さな仕切りをつけておけば、靴下・パンツ・ブラなどのアイテムごとにざっくり分類できます。畳む必要はなく、使ったあとはポンと入れるだけ。
ポイントは“分けすぎない”こと。分類が細かすぎると逆に面倒になってしまうので、「靴下ゾーン」「下着ゾーン」くらいのざっくり感がちょうどいいんです。中身が見えすぎないよう、上からふたをかけたり、不透明のボックスを使うと見た目もスッキリしますよ。
Tシャツや部屋着は「畳まず丸めてポン!」
毎日着るTシャツや部屋着は、畳むより“丸めてボックスへ”が断然ラク!パッと取り出せて、使ったらポンと入れるだけ。たとえシワになっても家で着る分には気にならず、手間も時間も節約できます。
収納に使うのは、深さのある布ボックスやかごがおすすめ。Tシャツは袖を軽く内側に折ってクルクルと丸めて、立てて並べておくと見た目もスッキリします。必要なものだけが見える状態になるので、選びやすさもアップ。
この方法は「一軍の部屋着」だけに適用するのがコツ。外出着やシワが気になる服はハンガー収納にまわして、日常的に使う服だけを投げ込み式にすれば、メリハリがつきます。畳むのが苦手な人でも、これなら続けられるはずです。
ランドリーバスケットを“そのまま収納”に
洗濯物を取り込んだあとの「しまう作業」が苦手な人には、思い切って“しまわない”方法もアリです。たとえば、洗濯物をたたまずにそのままランドリーバスケットに入れて使うスタイル。これなら畳む手間ゼロで、時間も労力も削減できます。
バスケットは、見た目にもおしゃれなものを選べば生活感が出にくく、インテリアにもなじみます。無印やニトリなどには、布製やワイヤータイプのスタイリッシュなランドリーバスケットがたくさんあります。
さらに「洗ったもの」「着たもの」の2つのバスケットを使い分ければ、簡単な仕分けも同時にできます。「これはラクすぎて戻れない」と感じる方も多い収納法です。収納とは「片付けること」ではなく、「生活しやすくすること」と考えると、このスタイルも立派な正解です。
ラベルを貼って“探さなくていい”工夫
畳まない収納でもう一つ大切なのが、「どこに何があるか」を自分で分かるようにしておくこと。見た目はざっくりでも、ルールが決まっていれば散らかりません。そのための工夫として効果的なのが、「ラベル貼り」です。
ボックスやかごに「靴下」「Tシャツ」「タオル」などのシールを貼っておけば、どこに戻すか迷わずに済みます。中身が見えないタイプのボックスでも、ラベルがあれば探す時間がグッと減ります。100均で売っている黒板シールやマスキングテープを使えば、手軽でおしゃれにラベルが作れます。
また、ラベルの位置は「自分が立ったときに見える場所」にすると便利です。特にクローゼット下や棚の奥など、見落としがちな位置は工夫が必要です。収納を“探す作業”にしないことが、続けやすさのポイントになります。
中身が見えない布かごで生活感オフ
畳まない収納をするときに気になるのが、「ごちゃついて見えないか?」ということ。でも大丈夫。中身が見えない布かごや収納ボックスを使えば、生活感を上手に隠せます。特にフタ付きの布製ボックスや、ふんわりしたフェルト素材のかごは、やさしい印象で部屋になじみやすいアイテムです。
「見せない収納」にするだけで、たとえ中がごちゃっとしていても外からはわかりません。インテリアに合わせて色や素材を統一すれば、棚の中に並べるだけで空間がスッキリ整って見えます。
さらに、カラーボックスなどにぴったり合うサイズを選べば、余計なスペースが生まれず効率的。無理に畳むより、「ざっくり入れて見せない」スタイルの方が、結果的に片付いた印象を与えてくれます。一人暮らしの部屋には特におすすめの収納法です。
“見せる収納”で畳まないのにおしゃれに見せるコツ
ワイヤーバスケットに入れて“生活感”を隠す
畳まない収納は「ぐちゃぐちゃして見えそう」と思われがちですが、実は“見せ方”を工夫すれば、逆におしゃれな印象になります。たとえば、ワイヤーバスケットを使って、あえて中身を少し見せるスタイルにすると、こなれた雰囲気に。
Tシャツや部屋着などは軽くたたんだり丸めたりしてポンと入れるだけ。中に布や紙袋を敷いて、内容が見えすぎないようにすれば、程よく生活感を抑えることができます。金属製のバスケットなら、インダストリアルやシンプルインテリアにもぴったりです。
バスケットを棚やラックに並べるだけで、“ディスプレイ収納”として成立します。中身がラフでも「整えて見せる」ことで、部屋全体の雰囲気がスッキリします。
洗濯物の色味で統一感を出すテク
収納は中身の色を意識するだけでも、グッとおしゃれに見せることができます。たとえば、モノトーンやアースカラーの服を集めて1か所にまとめると、たとえ畳んでいなくても「まとまり感」が出てごちゃつきません。
靴下やタオルも、似た色合いでまとめて見せると、自然と統一感が出て、見せる収納としての完成度が上がります。もしカラフルなアイテムが多い場合は、見せたくないものだけを布かごやボックスに入れ、見せたい色のアイテムを外に出す、という工夫も有効です。
“配色”を意識することで、インテリアとしても映える収納になります。アイテムそのものを変えなくても、「置き方」「色のバランス」だけで、印象は大きく変わります。
スチールラックにバスケットで魅せ収納
スチールラックとバスケットの組み合わせは、“畳まない収納”でもっとも実用的で見た目もおしゃれな組み合わせです。無印良品やIKEAなどで手軽に揃うスチールラックに、布製やプラスチック製のバスケットを差し込むだけで、収納棚が完成します。
この収納法のポイントは、“用途ごとにまとめること”。たとえば、上段にTシャツ、中段にパジャマ、下段にタオルなど、アイテム別に分けておけば、探しやすく使いやすい収納ができます。
バスケットの色や素材を統一すれば、スチールの無機質さとバランスが取れて、部屋全体が洗練された印象に。棚板の高さを自由に変えられるので、収納する物のサイズに合わせてカスタマイズしやすいのも魅力です。
折りたたみチェアを“ちょい置き場”に活用
「とりあえず置きたいけど、床に放り出すのはイヤ」そんなときに活躍するのが、折りたたみチェアやスツール。帰宅後に脱いだ服や、まだ洗ってないパジャマなど、“ちょい置き”の場所としてとても便利です。
畳まずに置くと雑然として見えがちですが、こうした“ちょっとした置き場”を設けることで、部屋が散らかりにくくなります。しかも椅子なら、使わないときは畳んでしまえるので、省スペースで邪魔になりません。
無印やIKEAなどのシンプルな折りたたみチェアは、部屋の雰囲気を壊さず、使いやすさも抜群。布をかけてカバーをするだけで、見た目にも柔らかさが出て、インテリアの一部として自然に溶け込みます。
畳まない=ズボラ、ではないおしゃれ感
“畳まない収納”というと、「ズボラに見えそう」と不安になるかもしれません。でも実は、それを“あえての選択”としておしゃれに見せる工夫をすれば、むしろセンス良く見えることもあるんです。
たとえば、ワイヤーバスケットや布かごに服を丸めて入れていたとしても、色や形に気を配れば十分に整って見えます。見せるところは見せて、隠すところは隠す。そんな“抜け感”のあるスタイルが今っぽい収納の考え方です。
実用性とビジュアルのバランスを取れば、「ラクだけど整って見える」空間が作れます。畳むかどうかにこだわるのではなく、自分の暮らしに合った心地よい収納スタイルを選ぶことが、長く続けられるコツです。
自分に合った「ラクする収納」の作り方
無理に畳まないことで続けられる
収納や片付けが続かない原因のひとつに、「完璧を求めすぎる」ことがあります。「きれいに畳まなきゃ」「ピシッと揃えなきゃ」と思いすぎると、日常生活の中でそれを続けるのは難しく、結果的に挫折してしまいがちです。
そこで大事なのが、「続けられるレベル」に合わせた収納方法を選ぶこと。毎回丁寧に畳むのではなく、「丸める」「投げ込む」「掛ける」など、無理なくできる方法に切り替えることで、ストレスを減らしつつ片付いた部屋をキープできます。
大切なのは、片付けを「きれいに見せる作業」ではなく、「生活しやすくする手段」と捉えること。見た目より、自分が使いやすく、負担にならない収納こそが、長く続けられる暮らしのベースになります。
毎日のルーティンと動線を見直す
収納は、“使う場所にあること”と“戻す動作が簡単であること”がとても大切です。つまり、自分の生活動線に合った収納にしないと、どんなに整理しても結局「戻すのが面倒」になってしまいます。
たとえば、部屋着やパジャマは寝室の近く、タオルは浴室の横など、使う場所に置くことで、動きがスムーズになります。また、洗濯物を取り込んだ流れでそのまま収納できるように、ランドリースペースのすぐそばにボックスを置くなどの工夫も効果的です。
動線を意識した収納は、「戻す」のハードルを下げ、片付けが自然と習慣になります。最初に少し考えて配置を工夫することで、日々の手間が大きく変わります。
“使う場所に収納”が鉄則
収納家具を増やしても、「使う場所から離れている」と結局は使いにくくなってしまいます。たとえば、洗面所で使うタオルをリビングの引き出しにしまっていては、取りに行くのが面倒になりますよね。
収納は“その場で完結”できるのが理想。洗面所にはタオルを、玄関には靴下やマスクを、ベッドのそばにはパジャマやブランケットを。そうすることで、自然と「戻す場所」も決まり、片付けも習慣化しやすくなります。
この「使う場所に収納する」という考え方を取り入れるだけで、暮らしの流れが整い、片付けのストレスがかなり減ります。収納は“インテリア”ではなく“生活の仕組み”として考えることが、ラクに暮らす第一歩です。
一人暮らしこそ「ほどよく手を抜く」工夫
一人暮らしではすべての家事を自分でこなさなければならない分、収納にも「完璧」を求めすぎると疲れてしまいます。そこでおすすめしたいのが、“あえて手を抜く”という選択。全部をきれいに畳んで、整えて…ではなく、「手を抜いても片付く仕組み」を作ることが大切です。
例えば、使ったものをとりあえず入れるかごを用意したり、毎日使う服はハンガーに掛けるだけにしたりと、無理のないスタイルを選ぶことが、自分の生活を守ることにもつながります。
「ちゃんとできない自分」を責めるよりも、「自分に合うやり方」に寄せていくほうが、長続きします。ラクしてもスッキリ暮らせる。そんな暮らしを作るために、少しの手抜きはむしろ大歓迎です。
「どう片付けたいか」を基準に選ぶ収納法
片付けや収納というと、「正解」があるように感じてしまいますが、実は人それぞれ暮らし方や性格、部屋の間取りも違うため、万人に合う収納法はありません。大切なのは、「自分がどう片付けたいか」を明確にすることです。
・畳むのが嫌いなら、掛ける収納
・出しっぱなしでもOKな見せる収納
・使ったら戻すが苦手なら、とりあえずボックスを用意
このように、自分のクセや生活スタイルに合わせて収納法を選べば、片付けがずっとラクになります。「人に見せる収納」より「自分に合った収納」を選ぶことで、ストレスが減り、快適な空間が作れます。
収納に“正解”はありません。自分が気持ちよく暮らせるかどうかを基準に、無理のない収納スタイルを見つけていきましょう。
まとめ
畳まなくても、暮らしはスッキリ整う
洗濯物を畳むのが苦手でも、「掛ける」「入れる」「置くだけ」で部屋は十分に整います。一人暮らしにおいて大切なのは、自分がラクで快適に続けられるスタイルを選ぶこと。
ハンガーやボックスを活用したシンプルな収納法なら、無理なく、でもきちんと感のある部屋をキープできます。
収納は“努力”ではなく“仕組み”です。畳まないからといってズボラなのではなく、「畳まなくても片付く」工夫をすることが、賢い収納術の第一歩。
今日からあなたの暮らしにも、“畳まない収納”を取り入れてみてはいかがでしょうか?